技術リーダーの一日
|
劉 功義さん
Kyndryl
Distinguished Engineer
|
 |
はじめに
|
Kyndryl社でデータ&AI推進を担うDE(Distinguished Engineer)の劉功義さんにお話を伺いました。
インタビューでは、キャリアの転機、障害対応へのこだわり、AI活用、そして日々の生活まで幅広く語っていただきました。
|
|
 |
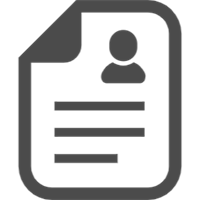 EXPERIENCE
EXPERIENCE
- 2006年:IBMに入社し、大和事業所に配属。社内システムの運用拠点でテープ、ストレージ、分散ファイルシステムの構築・運用を担当。
- 2008年頃:海運、製薬、公共、地銀、製造など多様な業界のプロジェクトに参画。IBM クラウドサービスやストレージ共用サービスの立ち上げにも参画。
- 2017年頃:保険のお客様担当アーキテクトとして、プライベートクラウドの企画・実装、運用自動化、Observabilityによる運用高度化、Site Reliability Engineer育成に取り組む。
- 2021年:Kyndryl にスピンオフ後、クラウド事業に所属し、次にアプリケーション、データ&AI 事業へ異動。デリバリーのラインマネジメントと技術的チャレンジを重ね、AI・データ事業の立ち上げに貢献。
- 社内外のコミュニティー活動(アーキテクト・コミュニティー、TEC-J、ITLMC、ストレージ・コミュニティーなど)を通じて多くの人と出会い、刺激を受けながら成長。
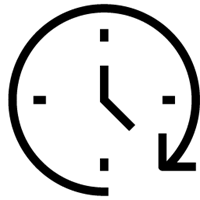 DAILY SCHEDULE
DAILY SCHEDULE
| 6:30 |
起床、子どものお弁当作り(妻と)、お見送り |
| 8:00 |
出社準備、通勤、Copilotを活用した情報収集や資料作成 |
| 9:00〜12:00 |
会議、資料作成、技術検証など |
| 12:00〜18:00 |
お客様との打ち合わせ、講演、フォローアップなど |
| 18:00 |
帰宅、夕食準備 |
| 21:00 |
グローバルチームと情報共有 |
| 22:00 |
子どもが就寝後、読書・研修・技術検証 |
| 24:00 |
就寝 |
Q&A:キャリアに関して
Q. IBM入社から現在までで、最も印象的だったキャリアの転機は何ですか?
A. まずはIBM入社です。大和事業所でEOS間近のシステム運用からキャリアをスタートしました。若手時代は障害対応が多く、ジョブ失敗、性能遅延、アクセス障害、業務復旧といったトラブル対応ではじめてのプロジェクトにレスキューで入ることもありました。次が2017年に保険お客様担当アーキテクトとしてIT全体を俯瞰するようになりました。さらに2021年のKyndryl転籍。そこでクラウド、次にアプリケーション・データ・AI領域へと業務が変化しました。
Q. 障害対応にこだわる理由は何ですか?
A. 障害対応は大変ですが、システムの状況を切り分けながら原因を特定し、例えば性能遅延であればボトルネックを見つけて解決したときの達成感が非常に大きいです。早期の業務復旧に向けた確実な問題分析の過程でアドレナリンが出るような感覚もあり、その凝縮された時間でシステムエンジニアとして多くの学びがありました。2年目ごろに先輩から「しっかりログを読め」と教わったことで、細かく見る力が身につきました。
Q. DE(Distinguished Engineer)になった理由を教えてください。
A. 先輩方から、技術者としてのバトンを受けるという意識が強かったです。過去に所属したテクニカル・コミュニティーのDEの方々の姿、そしてそのコミュニティーの先輩方が次々とDEになっていく姿に刺激を受け、プリンシパルになっていた自分も次にDEとして後進を引っ張る存在にならなければと思いました。1年にもわたるDE審査とその準備、推薦状の取得に高い壁がありましたが、技術者コミュニティーでの活動や 育成への思いが強く、挑戦を決意しました。先輩方に「B10 で組織を考える、BandDになったら国のことを考える」と言われていたことも大きな刺激でした。

参照:Kyndryl's 2025 Distinguished Engineers
Q. Copilotなど生成AIの活用について教えてください。
A. Copilot には、お客様の技術情報や学会のモニタリングをしてもらい、自分専用の知りたい情報の抽出をさせています。障害やエラー情報の分析をAIエージェントに任せることも進めていますが、ログを見る勘所が失われる懸念もあり、エンジニアに必要な能力の取得方法が変わってくると考えています。なお情報収集はCopilotに頼る以外にもACMなどの学協会の情報や MITレビュー、LinkedInなどのSNSを使い、Teamsなどで社内共有しています。
Q. 技術的チャレンジについて具体的に教えてください。
A. 常に変化する技術領域がチャレンジです。入社時にはストレージなどインフラに近い領域から、アプリケーションに近い領域へ業務が変化しました。どの技術チャレンジがあっても複数の視点で図を書きながらモデリングすることは共通しています。なおプロジェクトマネジメントの観点でも、体制図も一つの組織のモデリングですし、ステークホルダーを可視化することで、どのように円滑にプロジェクトを推進すべきかを把握しています。
Q. 研究活動はどのように進めていますか?
A. 土曜日に研究を進め、月 1 回程度ディスカッションを行っています。社会人になる前から大学で プロジェクトマネジメントの定量的管理を研究し、入社後も必要性を感じて継続。2015 年に学位を取得し、今も続けています。スキルの可視化やプロジェクトリスク分析などをテーマにしています。
Q&A:日々の生活に関して
Q. 家庭との両立で工夫していることはありますか?
A. DE になってから出社頻度が週 4〜5 回に増えたため、家事や洗濯はできるだけこまめにを心がけつつも土日にまとめて行っています。妻は医療従事者で休日出勤や夜勤もあるため、家庭内の役割分担を工夫しています。
Q. 読書や映画鑑賞はどのようなジャンルがお好きですか?
A. オライリーが多いのですが娘が勧めてくれた本、例えば「5分後に意外な結末」のような小説も楽しんでいます。
Q. 研修受講はどのような分野ですか?
A. セキュリティ、AI、データなど幅広い分野の研修を受講しています。夜の時間を活用して学びを深めています。
Q. 技術検証はどのようなことをされていますか?
A. 手元で動かせるコンテナ技術で、気になるテクノロジーを試してみています。今はMacのPodmanの上でdifyとollamaが動いています。実際に手を動かすことで理解が深まります。
Q. 得意料理は何ですか?
A. ラーメンです。特に高菜ラーメンが好評なのですが、子どもが嫌いな野菜も刻んで入れられるので親にも嬉しいです。最近のヒットはだし取り立てのなめこ汁でした。クリスマスのチキンも思い出深い料理ですが、鶏皮が不評でした。
 インタビューを終えての参加メンバーの感想
インタビューを終えての参加メンバーの感想
インタビューの冒頭から、劉さんが障害対応のご経験で、問題の本質を見極めて解決へ導くことに対する熱意が印象的でした。 技術的チャレンジや、入社当時から続けている研究活動について詳しく伺い、その探究心の強さを改めて感じました。
さらに、「自分が感じた経験を形に残したい、またみなさんが少しでも楽になるように残したい」という言葉からは、劉さんの後進育成への情熱が伝わってきました。
仕事・家庭・研究を見事に両立されている姿は、とても刺激的で、学ぶところが多かったです。
終始、優しい笑顔があふれ、穏やかな雰囲気の中で進んだインタビューは、あっという間の1時間でした。ご協力いただき、誠にありがとうございました。
技術者リーダーの一日 インタビュアー